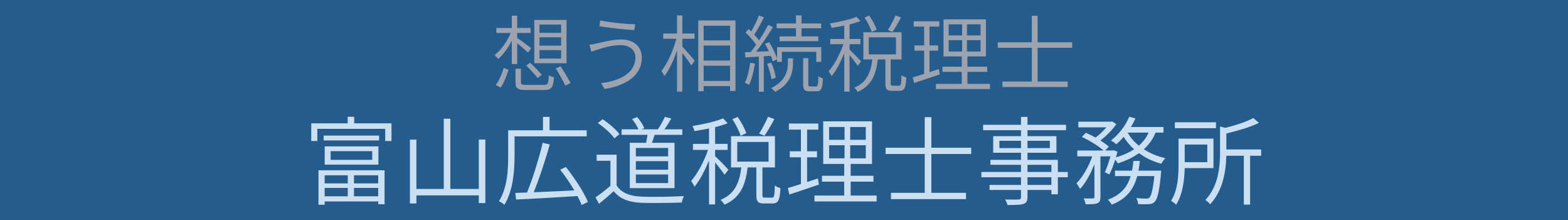相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺留分侵害額の請求を受けた場合の、小規模宅地等の特例の適用について、お話します。
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(遺留分侵害額請求の訴訟が提起されている場合の特例の適用(令和元年7月1日以後に開始した相続))
【誤った取扱い】
22 本年3月に死亡した父は、相続財産を全て長男に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたが、他の相続人から、遺留分侵害額請求の訴訟が提起された。
そのため、小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の選択についての同意が得られないとして、同特例を適用せず期限内申告書を提出した。
【正しい取扱い】
22 他の相続人から遺留分侵害額請求の訴訟が提起されていたとしても、長男は、遺言により不動産も含め相続財産の全てを取得しているのであり、小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の選択について他の相続人の同意を要しないから、同特例を適用して申告することができる(措令40の2⑤、相基通11の2-4)。
なお、相続税の申告期限後に、長男が他の相続人に対し遺留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなり、長男がこれに代えて小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地(以下「特例宅地」という。)の所有権を他の相続人に移転させたとしても、当該所有権の移転は、遺留分侵害額に相当する金銭を支払うための譲渡(代物弁済)と考えられ、長男が遺贈により特例宅地を取得した事実に異動は生じないことから、長男が小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなるということはない。
また、長男から特例宅地の所有権の移転を受けた他の相続人については、上記のとおり、相続又は遺贈により取得したものとはいえないため、特例の適用を受けることはできない。
金銭の支払が確定しても土地を相続することに変わりはない
裁判所HP(一部抜粋)
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
遺留分侵害額の請求を受け、その支払うべき金銭の額が確定したとしても、相続した土地は自分(長男)のものです。
相手(二男とします)に渡すのは「金銭」です。
同意が必要な相手は、「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人」(相続税の申告書第11・11の2表の付表1)です。
長男が「相続財産を全て」遺言で取得するのであれば、「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人」は、長男のみです。
他の相続人の同意は必要ありません。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
金銭の支払に代えて土地を移転した場合
長男が金銭の支払に代えて、二男に小規模宅地等の特例を適用して相続した土地を渡したとしても、所有継続要件等を満たせば、小規模宅地等の特例の適用はそのまま有効です。
 想う相続税理士
想う相続税理士