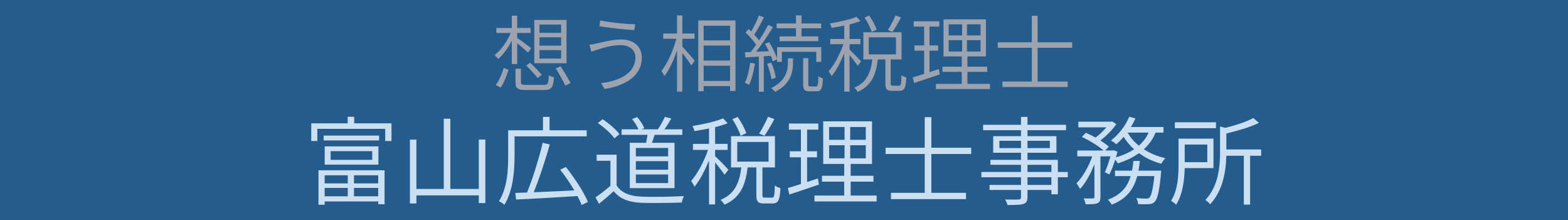相続税専門税理士の富山です。
今回は、下記の記事の逆パターン(亡くなった親御さんからの借入があったパターンではなく、亡くなった親御さんへの貸付けがあったパターン)について、お話します。
 相続により親からの借入の返済義務から逃れられる場合がある
相続により親からの借入の返済義務から逃れられる場合がある
親御さんの借入金(債権者は自分)を相続で承継した場合
例えば、あなたが親御さんに1億円を貸していたとします。
親御さんには、1億円の現金という財産と、あなたからの1億円の借入金という債務があることになります。
親御さんが亡くなったとします。
あなたがこの相続により、親御さんの手許にあった(元は自分が貸し付けた)現金という1億円の財産と、借入金という1億円の債務を相続・承継したとします。
これにより、あなたは、1億円の貸付けの債権者であると同時に債務者ともなるため、混同が生じて、その債権債務は消滅します。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
また、相続・承継した財産・債務がこれだけであれば、相続税もかかりません。
現金1億円から借入金1億円を債務控除すると、正味の遺産額はゼロだからです。
そして、現金1億円が手元に戻ってきます。
仮に、他に4,000万円の定期預金を相続したとしたら、正味の遺産額は4,000万円になるため、一定の場合には相続税がかかります。
親御さんの手許にあるのが現金ではなく建物の場合
あなたが親御さんに時価1億円(値下がりしないとします)の建物を時価で譲渡したとします。
本来であれば、その譲渡代金1億円をあなたがすぐに受け取ってもいいのですが、親御さんと準消費貸借契約を結び、売買代金相当額のお金を親御さんに貸している状態にしたとします。
親御さんには、時価1億円の建物という財産と、あなたからの1億円の借入金という債務があることになります。
親御さんが亡くなったとします。
あなたがこの相続により、(元は自分が譲渡した)建物という財産と、借入金という1億円の債務を相続・承継したとします。
これにより、あなたは、1億円の貸付けの債権者であると同時に債務者ともなるため、混同が生じて、その債権債務は消滅します。
時価1億円の建物が手元に戻ってきます。
この場合、相続税の申告は、上記と同じパターンになるでしょうか?
混同により消滅する債務の債務控除が一部認められなかった
相続税の計算では、建物は時価ではなく、相続税評価額で評価します。
建物(自用家屋)の相続税評価額は、「固定資産税評価額×1.0」です。
建物の時価と固定資産税評価額の間には差があります。
上記の時価1億円の建物の固定資産税評価額が6,000万円だったとします。
そうすると、相続税評価額は「6,000万円×1.0=6,000万円」です。
あなたがこの相続により、建物という6,000万円の財産と、借入金という1億円の債務を相続・承継し、建物6,000万円から借入金1億円を債務控除できるとすると、正味の遺産額は△4,000万円となります。
その場合には、他に4,000万円の定期預金を相続したとしても、正味の遺産額は、
建物6,000万円+定期預金4,000万円△借入金1億円=ゼロ
となるので、相続税はかからない、ということになるのでしょうか?
そうはならない、という裁決がありました。
出典:TAINS(J123-3-09)(一部抜粋加工)
令03-06-17公表裁決
《ポイント》
本事例は、請求人が被相続人と生前締結した建物売買契約(売主:請求人、買主:被相続人)に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務について、当該債務のうち、当該建物の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)を超える部分は、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎず、相続開始日現在における消極的財産価値を示すものとはいえないため、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとしたものである。
《要旨》
請求人が、被相続人と生前に締結した売主を請求人、買主を被相続人とする建物売買契約に伴い被相続人に生じた売買代金相当額の債務(本件債務)は、真正に成立した処分証書が存在し、法的に履行が強制されることから、その全額が相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当する旨主張するのに対し、原処分庁は、本件債務は履行を予定していないことから、その全額が「確実と認められるもの」には該当しない旨主張する。
しかしながら、本件債務の発生原因となった建物売買契約は、建物の売買金額と相続税評価額との間に生じる差額により相続税の軽減効果が期待できるとの提案があった上で締結されたことからすると、本件債務のうち、売買対象となった建物(本件建物)の経済的価値(評価通達に基づき算出された評価額)に相当する部分については、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示しているものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、いずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎないのであるから、相続開始日時点における債務としての消極的経済価値を示すものとはいえない。したがって、本件債務のうち、本件建物の経済的価値に相当する部分については、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するものの、本件建物の経済的価値を超える部分については、「確実と認められるもの」には該当しない。
 想う相続税理士
想う相続税理士