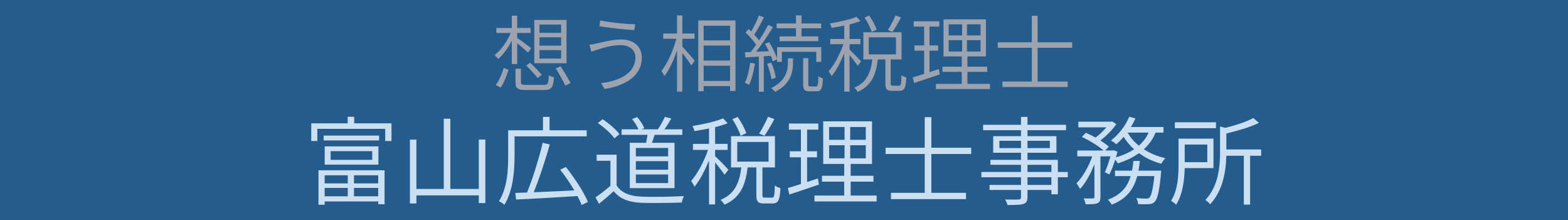相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における死亡退職金の取扱いについて、お話します。
死亡退職金はみなし相続財産
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
概要
相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
死亡退職金は、亡くなった方からもらうものではないのですが(会社等からもらいます)、相続を原因として経済的利益を受ける側面があるため、相続で取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
 想う相続税理士
想う相続税理士
相続税法(一部抜粋加工)
二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与
死亡後3年以内要件は「支給」ではなく「支給額の確定」を見る
相続税法基本通達(一部抜粋加工)
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とは、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものとする。この場合において、支給されることは確定していてもその額が確定しないものについては、同号の支給が確定したものには該当しないものとする。
死亡退職金が3年以内に実際に支給されていなくても、その支給額が3年以内に確定していれば、相続税の課税対象となります。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
相続税の申告期限後に支給額が確定した場合
申告期限までに実際に支給されていない場合であったとしても、その支給額が申告期限までに確定している場合には、相続税の課税対象になります。
逆に、申告期限までに支給額も確定していなければ、相続税の申告に計上する必要はありません。
ただし、申告期限後に支給額が確定し、その時期が死亡後3年以内である場合には、相続税の課税対象となりますので、相続税の期限後申告や修正申告が必要になる場合があります。
 想う相続税理士
想う相続税理士
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(相続開始後3年経過後に支給を受けた死亡退職金)
【誤った取扱い】
12 死亡退職金の支給額が相続開始後3年以内に確定し、3年経過後に実際に支給された場合に、当該死亡退職金が一時所得に該当するとして申告した。
【正しい取扱い】
12 相続開始後3年経過後に死亡退職金の支給を受けたとしても、3年以内にその支給される額が確定していた場合には、当該死亡退職金は相続財産となる(相法3①二、相基通3-30)。
なお、死亡退職金の支給額が相続開始から3年経過後に確定した場合には、相続人の一時所得となる。