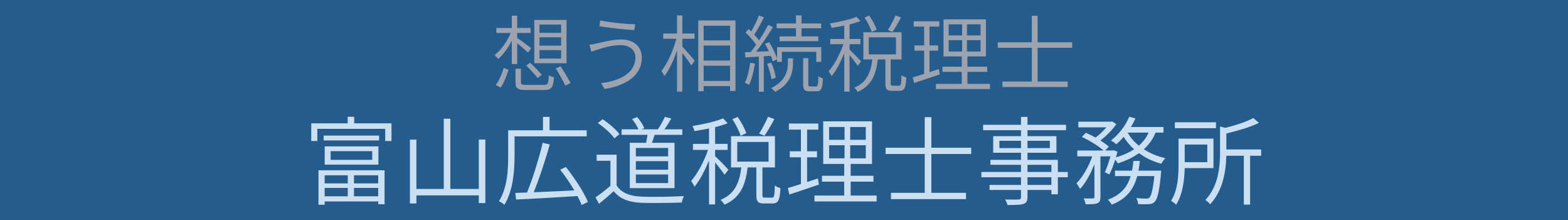相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の納税資金対策について、お話します。
相続対策には3つの柱がある
相続対策は、主に
- 遺産分割対策(遺産分け対策)
- 納税資金対策(納税資金準備対策)
- 節税対策(相続税の節税対策)
が3つの大きな柱になります。
「相続対策」というと、「相続=遺産を引き継ぐこと」が無事に終わるように、という意味で「『争族』対策」を指すこともあるかもしれません(上記の「遺産分割対策」に包含されます)。
「遺産分割対策」は、相続税がかかるかどうか(財産が多いかどうか)は関係ありません(財産が少なくてもモメルので)。
「相続『税』対策」という場合には、「節税対策」を指すことが多いかもしれません。
こちらは、相続税がかかる(つまり財産が多い)場合の話になります。
そして、相続税がかかる場合には、「納税資金対策」が必要になる場合があります。
納税資金対策は本当に必要か?
相続税がかかるからといって、必ずしも納税資金対策をしなければならない、という訳ではありません。
相続税が少なければ余裕で納税できるかもしれませんし、相続税が多くても、死亡保険金や(争族にならない前提ですが)相続財産である現預金等がたくさんあれば、余裕で納税できるかもしれません。
ですから、生前に納税資金対策を検討する場合には、「相続税がどれくらいかかるか?」「納税資金に充てることができる財産がどれくらいあるか?」を把握することが必要となります。
その把握をしてからでないと、納税資金対策の要否は判断できません。
相続税が少なかったりかからなかったり、納税資金に充てることができる財産が多かったりするのであれば、納税資金対策は必要ありません。
売却による納税資金捻出は精神的に大変な場合がある
上記の「納税資金に充てることができる財産」が死亡保険金や現預金等であれば問題ないのですが、買い手が付きそうな不動産(土地や建物)や上場株式の場合には、(物納や延納をしない前提でお話すると)それらを申告期限までに実際に現金に換える必要があります。
その際、売却の判断(いくらで売却するか・いつ売却するか)が求められます。
せっかくですから、できるだけ高く売りたいところですが、それが結構難しい。
「土地を1,000万円で売って欲しい」という人が現れたけど、そんなに安い金額じゃ嫌だ、と思って断ったら、その後は購入希望者が現れなかった、とか、「上場株式を高値で売ることができた!」と思ったら、次の日にはさらに爆上がりしていた、というような起こり得ます。
 想う相続税理士
想う相続税理士