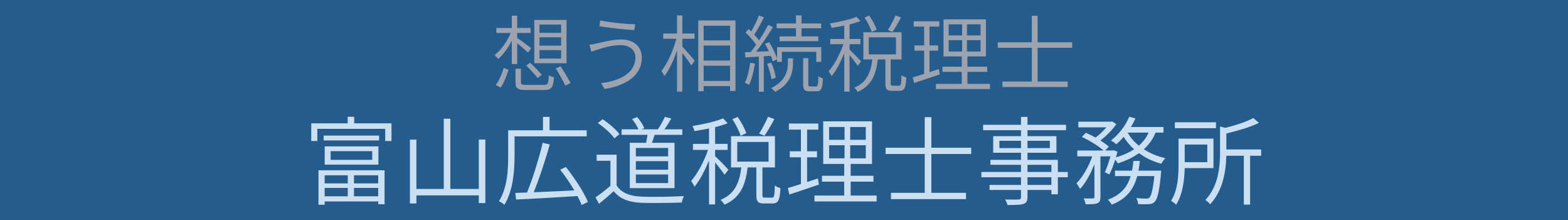相続税専門税理士の富山です。
今回は、令和6年分の贈与から新設された相続時精算課税贈与の基礎控除額及び申告不要制度の落とし穴について、国税庁HP・質疑応答事例を引用しながら、お話します。
相続時精算課税贈与の基礎控除額は絶対的非課税枠
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税には以前から110万円の基礎控除額があり、相続時精算課税には(特別控除額はありましたが、そして、今もありますが)基礎控除額はありませんでした。
ところが、令和5年度税制改正により、令和6年分の贈与から、相続時精算課税にも、110万円の基礎控除額が新設されました。
「基礎控除額はどっちも110万円なんだから同じでしょ?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
贈与税を計算する時に、この基礎控除額部分が非課税になるのは同じです。
ただし、違いが出るのは、相続税を計算する時です。
暦年課税による贈与については、相続で財産を取得した方が、亡くなった方から贈与を受けていて、その贈与日が生前贈与加算対象期間(令和7,8年の相続の場合には、相続開始前3年以内)に入っている場合には、基礎控除額(以下)の部分も、相続税の課税対象となります(1円の贈与でも相続税の課税対象)。
それに対して、相続時精算課税による贈与については、基礎控除額(以下)の部分は、相続税の課税対象とはなりません。
贈与税も相続税も絶対にかかりません(絶対的非課税枠)。
相続時精算課税による贈与の基礎控除額と特別控除額の違い
また、従来では、相続時精算課税による贈与をした場合には、1円でも申告をしなければならなったのですが、令和5年度税制改正により、(上記でお話した)新設された110万円の基礎控除額以下であれば、申告不要となりました。
110万円の基礎控除額を適用するだけの贈与であれば、申告は不要なのです。
正確に言うと、期限内申告をしても、期限内申告をしなくても適用できます。
ただし、2,500万円の特別控除額については、「その財産について期限内申告」をしなければ適用できません。
そうすると、こんなことが起こります。
その財産について期限内申告をしていないと特別控除額は適用不可
国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を提出する場合の相続時精算課税の適用の可否(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
【照会要旨】
甲は、X年に父である乙から株式Aの贈与を受け、贈与税の申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を提出しました。その際、甲は、株式Aの価額を100万円(相続時精算課税に係る基礎控除の額以下)と認識していたため、贈与税の申告書は提出していませんでした。
その後、株式Aの価額について評価誤り(正当額:500万円)が判明したため、贈与税の期限後申告書を提出することとなりました。
この場合、相続時精算課税を適用して贈与税額を計算できますか。
【回答要旨】
相続時精算課税を適用して贈与税額を計算することとなります。
ただし、株式Aについて贈与税の期限内申告書の提出がなかったため、相続時精算課税の特別控除は適用されません。
なお、X年分の贈与税額は、次の算式により計算した金額となります。
(株式Aの価額500万円△基礎控除額110万円△特別控除額0円)×20%=78万円
A株式が100万円だと思って(基礎控除額以下なので)期限内申告をしなかったら、500万円だった、基礎控除額110万円は期限内申告をしていなくても適用できるが、特別控除額は「株式Aについて期限内申告」をしていないので適用できないため、特別控除額が2,500万円もあるにもかかわらず、贈与税が発生してしまう、ということです。
 想う相続税理士
想う相続税理士
 暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の片方だけが110万円を超える場合の贈与税申告
暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の片方だけが110万円を超える場合の贈与税申告