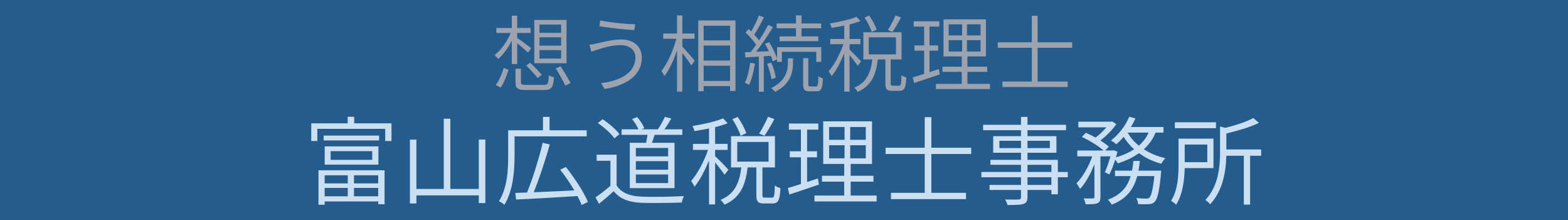相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税贈与に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税申告の注意点について、お話します。
住宅取得等資金の非課税贈与は持ち戻し不要
 住宅取得等資金の特例贈与は相続時精算課税を選択していても相続税の課税対象外?
住宅取得等資金の特例贈与は相続時精算課税を選択していても相続税の課税対象外?
上記の記事では、相続時精算課税贈与に係る特定贈与者が死亡した場合における相続税申告において、その特定贈与者から住宅取得等資金の特例の適用を受けた贈与を受けていた場合に、その贈与財産が相続税の課税対象になるかどうかについて、お話しました。
住宅取得等資金の非課税贈与については、相続税の課税対象とはならない、つまり、相続税の申告において、持ち戻し計算をする必要はない、ということなのですが、他の贈与(住宅関連以外の贈与)はどうなっているのでしょうか?
特定贈与者からの贈与で相続税申告において持ち戻しが不要なものとは?
相続税法基本通達を見てみます。
相続税法基本通達(一部抜粋)
21の15-1 相続税の課税価格への加算の対象となる財産
法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に贈与により取得した財産に限る(当該相続時精算課税選択届出書の提出に係る年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を除く。)。)のうち、法第21条の3、第21条の4、措置法第70条の2第1項、第70条の2の2第1項、第70条の2の3第1項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2第1項の規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないことに留意する。
(注)法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された措置法第70条の3の2第2項に規定する住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。
ただし、令和6年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る同項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。
上記の青太字の部分は、次のとおりです。
第21条の4:特定障害者に対する贈与税の非課税
措置法第70条の2(第1項):直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
第70条の2の2(第1項):直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
第70条の2の3(第1項):直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2(第1項):東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
つまり、これらの適用を受けて贈与税が最終的に非課税になった部分については、原則として、特定贈与者が死亡した際の相続税も非課税(課税対象外)、ということになります。
後から贈与税が課税される場合や相続税が課税される場合に注意
当初の贈与時には非課税だったとしても、後から贈与税が課税される(最終的に非課税にならない)場合や、相続税が課税される場合がありますので、ご注意を。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
 教育資金非課税一括贈与に後から贈与税が課税される場合
教育資金非課税一括贈与に後から贈与税が課税される場合
 亡くなった方が過去に教育資金非課税一括贈与をしていた場合の相続税申告
亡くなった方が過去に教育資金非課税一括贈与をしていた場合の相続税申告
 結婚・子育て資金の一括非課税贈与が贈与税・相続税の課税対象となるケースとは?
結婚・子育て資金の一括非課税贈与が贈与税・相続税の課税対象となるケースとは?
 想う相続税理士
想う相続税理士