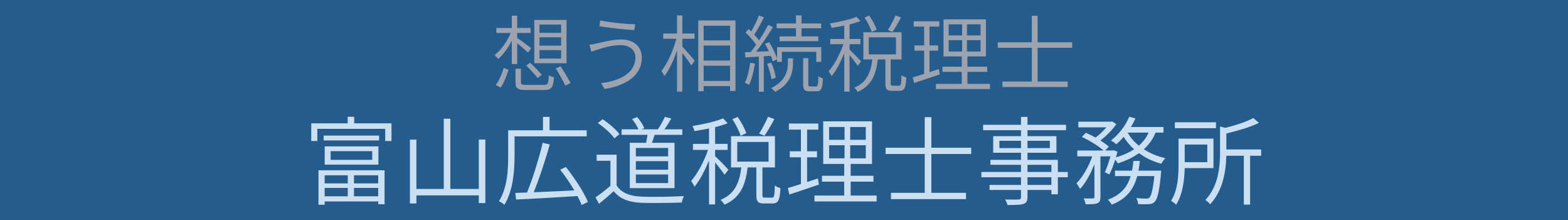相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税による贈与をして、贈与税の時効が成立した後に、その贈与財産の評価額が本当はもっと高かった(間違って安く評価してしまっていた)という場合における、相続税申告における取扱いについて、国税庁HP・質疑応答事例を引用しながら、お話します。
相続時精算課税贈与財産は相続税の課税対象になる
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「相続時精算課税」は、その名のとおり、「相続」の「時」に「課税」を「精算」します。
「『相続』の『時』」ですから、相続税が課税されます。
つまり、相続税が課税されるのですが、贈与時に贈与税を納付していたら、それを精算(相続税から差し引き)するのです。
ただし、令和6年分の贈与から、相続時精算課税による贈与に「基礎控除額」が創設されたのですが、この基礎控除額部分には、相続税は課税されません。
相続税は贈与財産のいつの時点の評価額に課税される?
令和5年3月31日に、長男甲さんは、父乙さんから、相続時精算課税による贈与により、A土地の贈与を受けたとします(この時のA土地の評価額は900万円)。
令和7年3月31日に、父乙さんが亡くなったとします(この時のA土地の評価額は1,000万円)。
父乙さんの死亡により、A土地には相続税がかかることになるのですが、A土地の評価額は、上記のとおり、毎年変動しています。
相続税が課税される金額、つまり、父乙さんの相続税の申告書に計上されるA土地の金額(評価額)は、贈与があった令和5年3月31日時点の評価額(900万円)でしょうか?それとも、相続が発生した令和7年3月31日時点の評価額(1,000万円)でしょうか?
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4103 相続時精算課税の選択
特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
「贈与時の価額」、つまり、上記の例ですと、令和5年3月31日時点の評価額(900万円)に対して、相続税が課税されます。
正しい評価額に対して相続税が課税される
上記のA土地について、相続時精算課税による贈与時に、間違って「500万円」と安く評価して贈与税の申告書を提出し、贈与税の修正申告をしようとしたら、時効が成立していて、申告ができなかった、という場合、相続税が課税されるのは「500万円」でしょうか?それとも「900万円」でしょうか?
国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について贈与税の除斥期間経過後に評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
特定贈与者からの贈与により取得した財産について、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額は、贈与税の除斥期間の経過日以後に贈与税の申告書等に記載された贈与財産の価額が評価誤り等により異なることを把握した場合であっても、その評価誤り等を是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額により計算した金額となります。
相続税が課税されるのは、正しい評価額である「900万円」です。
財産の評価額が変われば適用される基礎控除額も変わる?
上記のA土地の贈与が、令和5年3月31日ではなく、令和6年3月31日だったとします。
上記と同じく、贈与時の本当の評価額は900万円で、間違って申告した評価額は500万円だとします。
令和6年なので、110万円の基礎控除額を適用することができます。
長男甲さんは、同じ令和6年中に、相続時精算課税による贈与により、母から600万円の現金の贈与を受けていたとします。
2人別々の方から相続時精算課税による贈与を受けた場合、110万円の基礎控除額はどのように適用するのでしょうか?
贈与者(特定贈与者)父乙さん・母丙さんのそれぞれからの贈与について、110万円ずつ基礎控除額を適用できるのでしょうか?
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4410 複数の人から贈与を受けたとき
相続時精算課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分し、そのあん分した基礎控除額をそれぞれ特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から控除します。
長男甲さん1人につき110万円しか基礎控除額を適用することができません。
これを、父乙さんからの贈与分・母丙さんからの贈与分に按分します。
父乙さんからの贈与財産の評価額は(間違っているけど)500万円、母丙さんからの贈与財産の評価額は600万円です。
110万円の基礎控除額をこの評価額の比(5:6)で按分すると、
母丙さん:110万円×6/(5+6)=60万円
この金額で基礎控除額の適用を受けているはずです。
でも、よく考えてみると、父乙さんからの贈与について適用できる基礎控除額は、本当であれば贈与財産の評価額が500万円ではなく、900万円だった訳ですから、基礎控除額の按分は9:6となり、父乙さんからの贈与については、もっと基礎控除額が適用できたのではないでしょうか?
この場合における相続税の課税価格に加算される金額の計算に当たり、是正した後の財産の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除額については、是正後の財産の価額に基づき再計算した金額ではなく、贈与税の申告書等に記載された相続時精算課税に係る基礎控除額となります。
基礎控除額の適用については、50万円で(時効で修正申告ができずに)確定しているため、50万円分しか適用できません。
 想う相続税理士
想う相続税理士