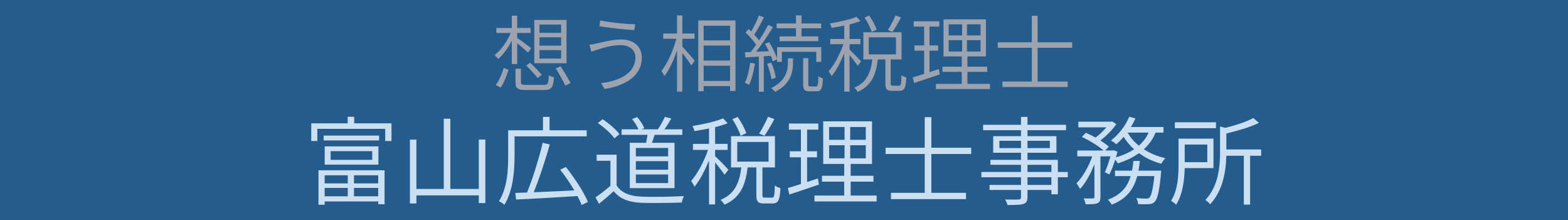相続税専門税理士の富山です。
今回は、「混同」について、お話します。
あなたの借金が消滅する時
民法(一部抜粋)
第四款 免除
第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
あなたが借金をしていて(この場合、あなたが「債務者」で、お金を貸してくれた人が「債権者」です)、債権者が「もうお金を返さなくていいよ」と、自分があなたに持っている債権を放棄すると、あなたの債務は免除され、その債権債務は消滅します(無くなります)。
民法(一部抜粋)
第五款 混同
第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない
あなたが借金をしていて(この場合、あなたが「債務者」で、お金を貸してくれた人が「債権者」です)、債務者であるあなたが同時に債権者になったら、これまた上記と同じように債権債務は消滅します(無くなります)。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
これを「混同」というのですが、債務者が同時に債権者になる、なんてことがあるのでしょうか?
相続で混同が発生する
例えば、あなたが親御さんからお金を借りているとします。
この場合、あなたが「債務者」で、親御さんが「債権者」です。
つまり、あなたは債務を返済する義務を有し、親御さんはあなたから返済を受ける権利(債権=貸付金)を有します。
親御さんが亡くなったとします。
親御さんのあなたに対する貸付金は消えません。
貸付金という債権は相続財産となります。
誰かが相続すれば、あなたから返済を受けることができるからです(お金になります)。
しかし、その債権をあなたが相続したらどうなるのでしょうか?
そうです、上記の混同が生じ、その貸付金は消滅します。
混同が生じても亡くなった時点では債権(貸付金)はある
出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(混同により消減した相続人に対する債権)
【誤った取扱い】
14 相続人乙は、被相続人甲から500万円を借用していた。甲の死亡により、乙は、甲の乙に対する債権500万円を相続したが、当該債権は、民法520条(混同)の規定に基づき消滅したため、相続財産として計上しなかった。
【正しい取扱い】
14 乙が、甲の有していた乙に対する債権を相続することにより、債権者と債務者が同一人となることから、当該債権は消滅するが、これは、あくまでも当該債権を乙が相続した結果生じる法律効果であり、当該債権を相続により取得した事実をも消滅させるものではないから、当然に相続財産に計上しなければならない。
混同が生じたことにより、自分の債務(借入金)は消滅しますが、だからといって、貸付金という相続財産が無くなる訳ではありません。
貸付金があるから、借入金が貸付金と同時に無くなる(消滅する)のです。
貸付金が無いというのであれば、あなたの借入金は消滅しません。
結果として貸付金が無くなったとしても、その混同による借入金の消滅により、あなたは「返済しなくても良くなる」という経済的利益を享受することになりますから、相続税が無税になる(相続財産が無くなる)訳はありません。
 想う相続税理士
想う相続税理士