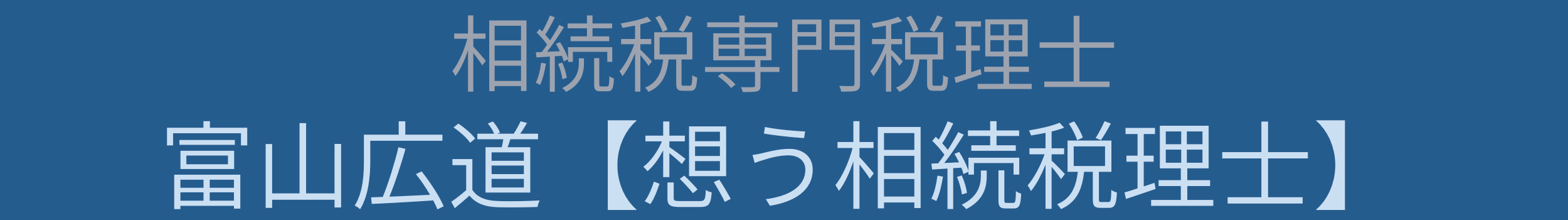相続税専門税理士の富山です。
今回は、贈与が成立していたと認められるようにしておくことの重要性について、お話します。
相続時精算課税でも暦年課税でも「贈与の成立」が前提
相続時精算課税制度は、原則として、親や祖父母(60歳以上)などから18歳以上の子や孫などへの贈与に対し、一定の非課税枠(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)を設けることで、財産の早期移転を後押しする制度です。
令和6年分の贈与からは、年間110万円の基礎控除額以下なら申告不要・相続財産への加算不要となるなど、制度も柔軟に進化しています。
しかし、この制度を利用する前提として、「贈与が確実に成立していること」が最も重要な条件となります。
この点は、暦年課税であっても同様です。
たとえ、税務署に相続時精算課税選択届出書を提出していても、実際に贈与が成立していなければ、制度の適用以前に「贈与そのものがなかった」と判断されます。
結果として、財産は贈与者(特定贈与者)に帰属しているものとされ、その後の相続時に、相続財産として相続税の課税対象となるのです。
記録がなければ「贈与はなかった」ことにされるおそれも
相続税の税務調査では、「名義は子や孫になっているが、本当にその財産は贈与されたものなのか?」という点が厳しく確認されます。
たとえば、以下のようなケースでは、贈与が否認される可能性が高まります。
贈与財産の移転が現金手渡しで、通帳記録が残っていない(お金の流れを説明できない)
子や孫の名義の口座が、実質的には親や祖父母が管理していた
贈与されたとされる財産が、その後も贈与者によって自由に使用されていた
これらの状況では、(仮に形式的には贈与があったように見えるとしても)「実質的な所有者が移っていない」=「贈与は成立していない」と判断されるリスクがあります。
その結果、相続時には「贈与されていない財産」として相続税の課税対象となるのです。
相続時精算課税により贈与された財産であっても、贈与の成立が証明できなければ、当然ながら制度適用の対象外となり、相続財産として計上されることになります。
つまり、制度を正しく選択したとしても、贈与自体が成立していなければ、節税効果はまったく得られないということです。
贈与が成立していても記録がなければトラブルの火種に
贈与がきちんと成立していたとしても、その事実を裏付ける書類や記録がなければ、遺産分割協議や相続税申告、さらには、その後の税務調査等において、(相続人間の、または、税務署との間の)誤解やトラブルが生じやすくなります。
そのような事態を防ぐためにも、贈与を行った際には以下のような対応を徹底しましょう。
振込記録や通帳の写しで金銭の移転を明示
贈与税の申告書控の保存
贈与財産の内容と評価額が分かる資料の整備
こうした対応は、相続時精算課税・暦年課税のいずれを選んだ場合でも共通して重要なポイントです。
相続時精算課税制度を利用していても、贈与の成立が証明できなければ、その財産は「移転していなかったもの」と見なされ、最終的には贈与者の相続財産として相続税の課税対象となります。
これは、贈与が成立していた場合に相続時精算課税制度によって相続税の課税対象となる仕組みと「見かけ上は同じ」でも、制度が適用されなかった分だけ納税者にとって不利となることがあるため、見過ごすことはできません。
 想う相続税理士
想う相続税理士
不安な点があれば、相続税専門の税理士に相談し、贈与の事実を確実に証明できる体制を整えておきましょう。