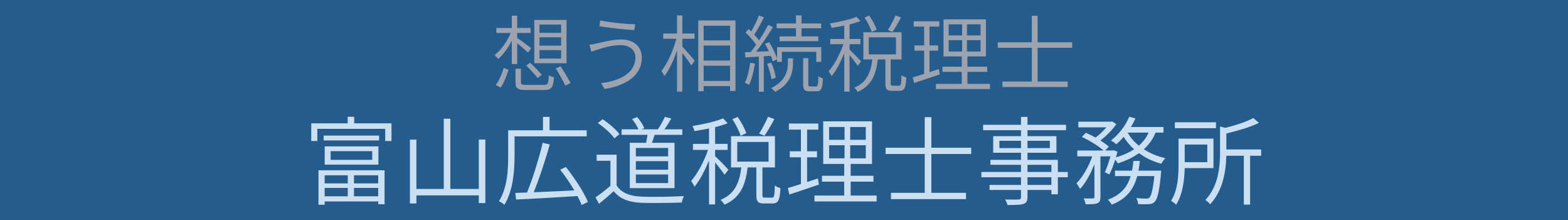相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度の概要について、お話します。
相続時精算課税制度とは?暦年課税との違いも整理
相続時精算課税制度とは、原則として贈与者が60歳以上の親または祖父母であり、受贈者が18歳以上の子や孫である場合に選択できる特例贈与制度です。
この制度を選択すると、その贈与者(特定贈与者)からの贈与については、毎年の贈与額からまず110万円の基礎控除額を差し引き(特定贈与者が複数いる場合には贈与額で按分計算)、それを超える金額について2,500万円までの特別控除額が適用されます。
令和5年分以前の贈与については、この「年間110万円の基礎控除額」はありませんでしたが、改正により、暦年課税とは別に、相続時精算課税制度の下でも毎年110万円の非課税枠が使えるようになりました。
これは実質的な減税措置であり、小口の贈与にも制度が使いやすくなったといえるでしょう。
また、2,500万円の特別控除額を超える部分には一律20%の贈与税がかかりますが、将来、相続が発生したときには、これまで相続時精算課税により贈与された金額のうち、基礎控除額を超える部分がすべて相続財産に加算され、今度は相続税の課税対象となります。
その際に既に納めた贈与税は相続税から控除され、控除しきれなかった金額については還付を受けることができます。
相続時精算課税制度選択時の注意点とデメリット
この制度は、一度選択すると撤回できない点に注意が必要です。
また、その贈与者(特定贈与者)からの贈与については、それ以後は暦年課税を選ぶことができなくなるため、制度の特徴や今後の相続(税)対策・計画に合致しているかを慎重に見極める必要があります。
さらに、以下のようなリスクもあります。
贈与された財産が不動産の場合、登録免許税や不動産取得税が相続時より高額になる(不動産取得税は相続時にはかからない)
贈与された財産が土地等の場合、相続時に小規模宅地等の特例が使えないため、節税策が限定される場合がある
このように、制度にはルールと注意点が多いため、「何となくトクになりそうだから使う」ではなく、財産承継計画の一環として慎重に判断して選択することが重要です。
この制度が向いている人・向いていない人
相続時精算課税制度は、以下のような方に向いています。
(最終的に節税できるかどうかは別として)一度に多額の財産を贈与して、資産移転を進めたい方
収益物件を早期に贈与して子や孫を支援したい方
絶対に非課税で贈与したい方(基礎控除額の活用)
一方で、以下のような方には慎重な検討が必要です。
相続税と贈与税の税負担の差を見据えて柔軟な資産移転を考えている方
小規模宅地の特例適用を重視している方
 想う相続税理士
想う相続税理士
そのため、相続税専門の税理士に相談し、将来まで見据えた選択をすることが何より大切です。