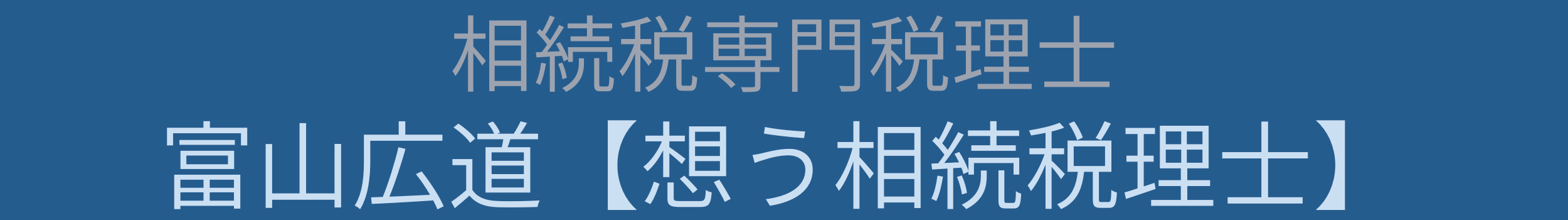相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税適用財産には「小規模宅地等の特例」が使えない、ということについて、お話します。
小規模宅地等の特例とは?相続税対策の大黒柱
相続税の節税策として非常に重要な制度のひとつが、「小規模宅地等の特例」です。
相続税の計算において、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができ、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
たとえば、「(3)特定居住用宅地等」であれば、最大330㎡までの部分について、評価額を最大80%減額できるため、大きな節税効果を生む場合があります。
しかし、相続時精算課税制度を使って生前に贈与された土地は、この特例の対象にならないという大きな制約があります。
相続時精算課税贈与をした土地等には特例が使えない
小規模宅地等の特例は、「相続」または「遺贈」によって取得した宅地にしか適用されません。
つまり、「贈与」によって取得した宅地は対象外なのです。
相続時精算課税により贈与された財産は、将来の相続税計算時に「『相続財産』として持ち戻される」にもかかわらず、法律上はあくまで「贈与財産」として取り扱われます。
そのため、小規模宅地等の特例の対象とはならず、大幅な評価減が認められないという矛盾のような現象が生じるのです。
たとえば、父親の住む自宅の土地を、相続時精算課税制度を使って生前に同居していた子が取得した場合、将来の相続時にその土地を持ち戻して相続税を計算することになるのですが、特例の80%減額は使えません。
同じ土地を「相続」で取得していれば大幅な節税ができたのに、制度選択によってそれが不可能になる、ということが起こるのです。
これは、相続税全体の負担に直結する重大なデメリットです。
制度選択による損得は長期的な視点で判断を
このように、相続時精算課税制度は、土地などの不動産を贈与する場合には特に慎重な判断が求められます。
節税効果の高い小規模宅地等の特例が使えないことで、かえって不利になるケースがあります。
特に以下のようなケースでは注意が必要です。
不動産の評価額が高額であり、80%(または50%)の減額効果が大きいと見込まれる場合
遺産分割協議の対象から外れてしまうことで、他の相続人との調整が難しくなる可能性がある場合
相続時精算課税制度には、「2,500万円の特別控除額」や「納税済贈与税の還付」などの魅力的なメリットがありますが、同時にこのような制度に起因する適用除外の落とし穴も存在します。
 想う相続税理士
想う相続税理士
このような重要な制度との適用関係まで含めて、贈与のタイミングや方法を決定する必要があります。
特に土地等の贈与を検討する場合には、相続税専門の税理士に事前に相談することで、後悔のない相続税対策につながります。