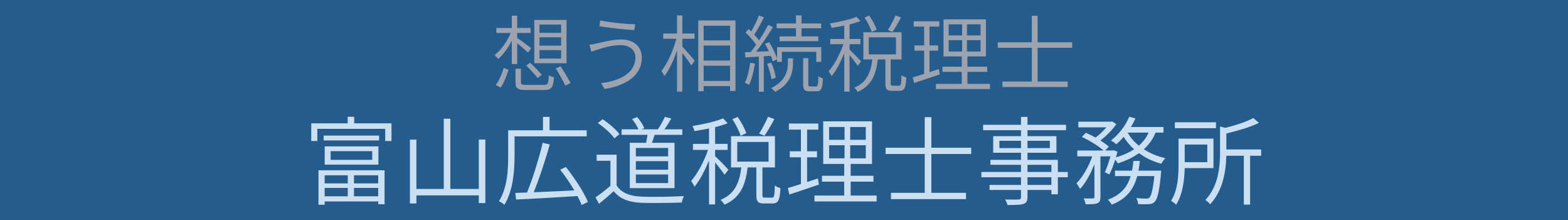相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例について、お話します。
相続税の申告における小規模宅地等の特例とは?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。
特定居住用宅地等の中の家なき子特例の質問が多い
相続税申告をご依頼いただく際、「うちは『家なき子特例』は適用できますか?」と質問されることがあります。
お母様が亡くなり、相続人が長女Aさんと二女Bさんの2人だとします。
お母様はご自宅(持ち家)にお一人で住んでいたとします。
長女Aさんは旦那さんの持ち家にずっと住んでいるが、二女Bさんは旦那さんの親御さんの持ち家にずっと住んでいる、という場合、二女Bさんがご自宅を相続すれば、家なき子特例を適用できるかというと、旦那さんの親御さんは「三親等内の親族」に該当するため、家なき子特例は適用できません。
長女Aさんは旦那さんの持ち家にずっと住んでいるが、二女Bさんはアパートにずっと住んでいる、という場合、二女Bさんがご自宅の敷地を相続すれば、家なき子特例を適用できる可能性があります。
この場合、遺産分割協議において、ご自宅の敷地を二女Bさんが取得し、小規模宅地等の特例を適用すれば(適用できれば)、相続税が安くなります。
「実家の土地建物は相続が終わったら売ってしまおう。どうせ売っちゃうんだからどっちが相続しても同じだ」という訳ではありません。
家なき子特例というと、持ち家がある人はダメ、と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
持ち家に相続開始前3年以内・相続開始時に住んでいなければ、適用の可能性があります。
小規模宅地等の特例の取得者要件は「親族」であって「相続人」ではない
お父様が亡くなり、相続人が長男Cさんと二男Dさんの2人だとします。
お父様はご自宅(持ち家)にお一人で住んでいたとします。
長男Cさんも二男Dさんも自分の持ち家に住んでいる場合、遺産分割協議によりどちらがお父様のご自宅の敷地を相続しても、小規模宅地等の特例は適用できません。
しかし、遺言により孫Eさん(長男Cさんの長女)が取得した場合、孫Eさんがアパートにずっと住んでいたりすれば、家なき子特例を適用できる可能性があります。
孫ではなくても大丈夫です。
小規模宅地等の特例は、取得者が「親族」であることが要件となっています(孫は親族に該当します。親族であれば絶対にOKという訳ではありません)。
民法(一部抜粋)
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
お父様の従兄弟の孫は、ギリギリ「六親等内の血族」に該当するため、亡くなった方の従兄弟のお孫さんが亡くなった方のご自宅の敷地を遺言で取得した場合、その方がアパートにずっと住んでいたりすれば、家なき子特例を適用できる可能性があります。
 想う相続税理士秘書
想う相続税理士秘書
 想う相続税理士
想う相続税理士