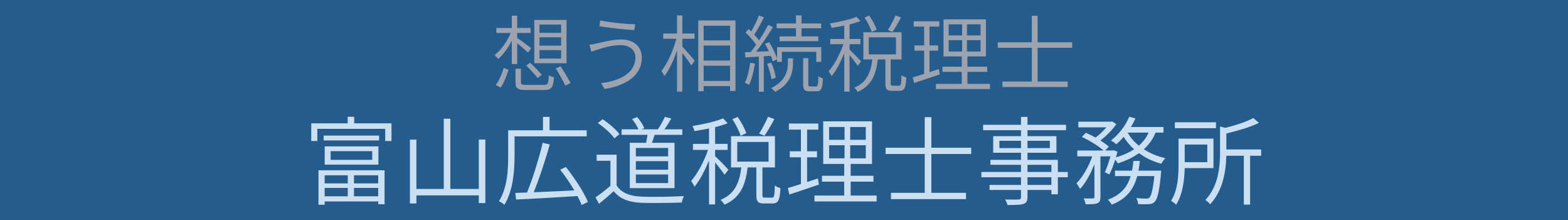相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産の中に非上場会社の株式(非上場株式)があり、その非上場会社が直前期末から相続開始日までの間に配当をした場合の類似業種比準価額の修正について、お話します。
類似業種比準価額から配当金の金額を控除する
財産評価基本通達(一部抜粋)
184 類似業種比準価額の修正
180《類似業種比準価額》の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。
(1) 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合
180《類似業種比準価額》の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額
非上場株式の評価における類似業種比準価額の計算において、直前期末から相続開始日までの間に配当金交付の効力が発生した場合(株主総会で決定した場合)には、通常の類似業種比準価額の評価額から、その配当金の金額を控除します。
これは、配当金交付の効力が発生した後の株式は、配当を受ける権利が無くなった分だけ、株価が安くなっている(価値が下がっている)と考えられることに基づくものです(いわゆる「配当落ち」の状態です)。
一方、亡くなった方は株主として相続開始日までにその配当金を収受しますから、亡くなった方の現金預金(という相続財産)は増加します。
入金される前に亡くなったとしても、そのもらうべき配当金の金額は「未収配当金」として相続税の課税対象になります。
会社から亡くなった方に配当金という現金が移転し、亡くなった方の財産が増加し、会社の財産が減っている、とも考えられます。
だとすれば、会社の株式の評価額にそれを織り込まないと、二重課税が生じてしまいます。
そこで、配当金の金額を控除することにより、二重課税を排除するのです。
純資産価額からは配当金の金額を控除しなくていいの?
「類似業種比準価額について上記のような対応をするのであれば、純資産価額についても配当金の金額をマイナスしなければならないのでは?」とお思いになった方もいらっしゃるかもしれません。
純資産価額の計算においては、既に配当金の支払は織り込み済みです(正しく計算していれば)。
仮決算方式の場合には、配当金を支払った分だけ、現金預金が減っているハズです。
また、(配当金の支払が確定していても)出金がまだの状態で相続が発生した場合には、「未払配当金」が負債の部に計上されているハズです。
直前期末方式の場合には、「未払配当金」が負債の部に計上されているハズです。
 想う相続税理士
想う相続税理士