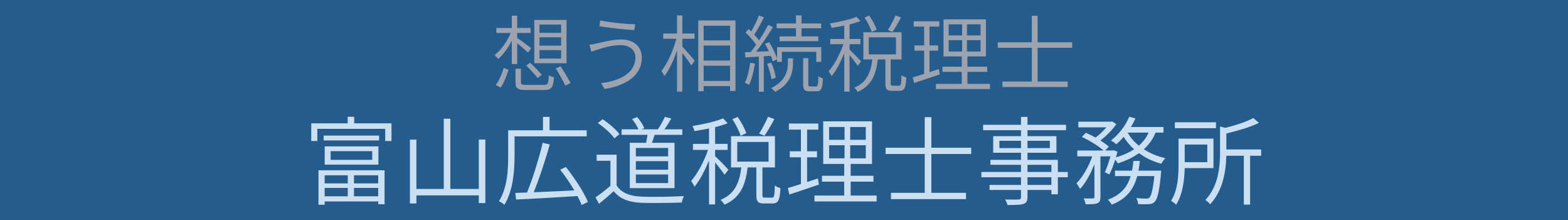相続税専門税理士の富山です。
今回は、非上場株式の「相続税申告における財産評価基本通達に従って計算した相続税評価額」が、その後の「M&Aにおける譲渡予定価格」よりメチャクチャ安くてもいいのか?が争われた判決について、お話します。
出典:TAINS(Z888-2667)(一部抜粋加工)
令和6年8月28日判決
売買代金が交換価値を反映しているとは限らない
取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得ないものであって、(現に、控訴人は、株式会社◯◯◯◯◯◯◯に評価を委託している。)、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に推測することが可能であるとは必ずしもいえない。とりわけ、M&Aが行われる場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らないというべきである。このことは、結果的に、専門的評価により交換価値と評価通達180に定める類似業種比準価額とのかい離の程度が著しいと判定された場合においても変わらないのであって、本件相続株式について、譲渡予定価格(10万5068円)と本件算定報告額(8万0373円)が比較的近く、これらが本件通達評価額(8186円)と大きくかい離しているからといって、更正処分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格が交換価値を反映したものであるとして、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存在していたということにはならない。
非上場株式の時価を正確に評価することには大変な困難が伴うため、評価額を算出した(評価額が算出されている)としても、それが絶対に正しいとは言えない、ということです。
譲渡予定価格について基本合意していてもそれは確定ではない
控訴人は、最高裁昭和61年12月5日第二小法廷判決を参照した上で、相続開始時に売買契約成立に至っていなかったとしても、近い将来売買契約が成立し、売買代金債権に転化する蓋然性が高い場合には、当該株式の価値が現実的に実現する蓋然性が高いものとして、当該株式の価値としては、その売買代金相当額が一つの基準になり得るところであるとも主張する。しかし、上記最高裁判決は、本件のように、売買契約が未だ成立していない場合とは明らかに状況を異にするものであり、近い将来における売買契約の成立及び売買代金債権への転化の蓋然性の程度を基準にすることは適切でない。なお、仮に、上記蓋然性の程度を基準とすることが許容されると解したとしても、相続開始日において、被控訴人らとV社との間で本件相続株式の売買契約が成立し、譲渡予定価格による売買代金債権に転化する蓋然性が高かったと認めることはできない。
契約が成立していないのであれば、その値段で売れるかどうかもまだ分からない、ということです。
租税回避行為があったとは言えない
最高裁令和4年判決は、評価通達6の適用の有無に当たり、被相続人が、相続税の負担を減じ又は免れさせる行為をしたことを考慮しているところ、被相続人及び被控訴人らによるこれに類する行為があったとは認め難い。被相続人又は被控訴人らが、相続税の負担を減じ、又は免れさせる行為をしたと認めることができない以上、被相続人又は被控訴人らの行為に着目した場合に、他の納税者との関係で不公平であると判断する余地はない。
評価が安くなるように画策することなく、潜在的に高く売却できる非上場株式を、財産評価基本通達に従って評価することは、租税回避行為ではない、ということです。
 想う相続税理士
想う相続税理士
 相続後に同族会社の株式を高値で売却したらタワマンみたいに総則6項で否認される?
相続後に同族会社の株式を高値で売却したらタワマンみたいに総則6項で否認される?