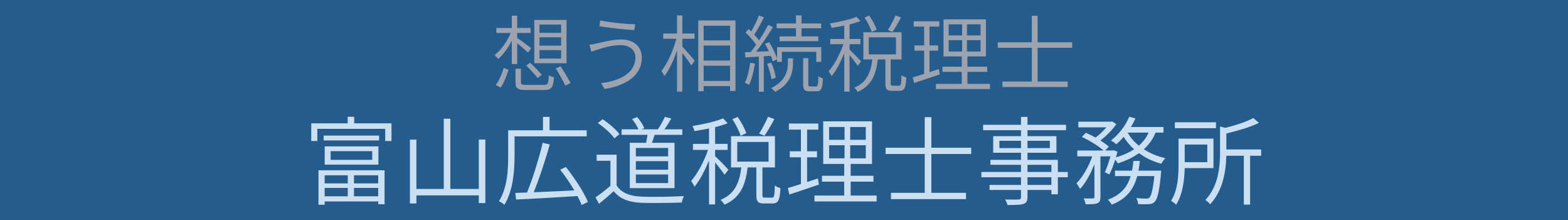相続税専門税理士の富山です。
今回は、不動産の本当の所有者は誰か?ということについて、お話します。
お金を払わず不動産の所有者として登記名義人等になったら贈与
相続税法基本通達(一部抜粋)
9-9 財産の名義変更があった場合
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。
贈与は、
民法(一部抜粋)
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
と定められているとおり、贈与者(あげる人)・受贈者(もらう人)双方の「あげる」・「もらう」という意思が必要となります。
しかし、親族間の贈与だと(通常、他人にタダで財産をあげたりしませんから、贈与はホボ親族間で行われますよね)、双方の意思が曖昧なまま財産が移転したりして、贈与が成立したのか分かりづらい場合があります。
そこで、タダで不動産の所有者登記名義人等になった場合には、原則として、お金を出してくれた人から贈与により取得したものとする、ということになっています。
このブログでも度々お話しているとおり、基本的に、財産の所有者は「お金を出した人」です。
「形式上の所有者となっている方」のモノではありません。
Aという財産につき、親が購入資金を出して、形式上の所有者を子供にしたとします。
この場合、「お金を出した人」は親なので、親が亡くなった時に親の相続財産となります。
しかし、親が亡くなった時に、子供に「贈与でもらったんですよ」と言われると、税務署は(時効で)税金を取れなくなってしまう場合があります。
「お金を出さずに不動産等の形式上の所有者になったら原則贈与だよ(贈与税を課税するよ)」ということにしておけば、税務署は贈与の時点で贈与税の課税ができる、ということになります。
タダで名義を取得してもお金を出した人の財産(名義財産)とされた事例
お金を払わず不動産の所有者として形式上は登記名義人になっているとしても、お金を出してくれた人から所有者登記名義人に贈与があったことにはならない(上記の通達の取扱いのようにはならない)、お金を出してくれた人(亡くなった方)のモノ(相続財産)だ、とした事例があります。
出典:TAINS(Z265-12626)(一部抜粋加工)
平成27年3月13日判決
相続税法基本通達9-9が、他の者の名義で新たに不動産を取得した場合には、当該行為は、一定の例外的な事実が認められない限り、原則として贈与として取り扱うものとしているのは、多くの事案を処理する課税庁が、贈与税の課税処分を行う際に贈与の事実の有無を統一的に認定し、税負担の公平を確保するために、内部的な指針を定める趣旨であると解される。
ところで、課税処分は、原則として、実体法上の権利関係に基づいてされるべきものであり(所得税法12条参照)、この実質課税の原則(相続税法にも妥当すると解される。)の下においては、実体的に贈与がないにもかかわらず、他人名義による財産の取得行為があったというだけで、贈与があったものと取り扱い、贈与税を課すことが許されないことは明らかというべきであり、上記各通達がそのような取扱いを認める趣旨であると解することもできない。
相続税法基本通達9-9を逆手に取って、過去に贈与があったことにする(贈与税は時効)、相続財産には該当しない、ということにはできない、ということです。
実体的に贈与が成立していれば当然贈与
上記の通達と事例を見て、「税務署の判断で『贈与』にも『相続(名義財産)』にもできるのか!ヒドイ!」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
あくまでも税務は実質で判断しますから、お金を出さずに不動産等の形式上の所有者になり、それが双方の合意(意思の合致)の元に行われているのであれば、贈与が成立しますので、「贈与」です。
上記の事例では、そのような「贈与」自体が成立していなかった、判断されました。
不動産については、不動産登記簿に所有者として登記されている者が所有者であると事実上推定すべきであるが(最高裁昭和34年1月8日第一小法廷判決・民集13巻1号1頁)、当該不動産の取得の経緯、取得原資の出捐や使用収益の状況、登記名義人と取得原資出捐者や使用収益者との関係等を総合考慮して、登記名義人以外の者に帰属するというべき特段の事情があると認められる場合には、その者を当該不動産の所有者と認定するのが相当である。
そうであるところ、前記認定のとおり、本件J不動産については、平成9年3月●日付けで原告甲(相続人)を所有者とする所有権移転登記がされているものの、その競落のための手続は、亡B(亡くなった方)の指示により、亡Bが事業主体であったKの従業員が行い、その取得原資も亡Bが拠出している上、亡Bが、原告甲に相談することなくKの事務所として使用していたのであって、亡Bが、同不動産について、固定資産税を負担し、所得税の申告に当たって減価償却費を計上していたこと、原告甲が、本件J不動産について原告甲名義で所有権移転登記がされたことをKの従業員から事後的に知らされたのみであり、亡Bから贈与の申込みを直接受けておらず、受諾の意思表示もしていないものと認められること等をも考慮すれば、本件J不動産を実質的に取得したのは亡Bであったと認めるのが相当である。そして、その後、亡Bが同不動産を原告甲その他の者に譲渡したことをうかがわせる事情は認められない。
そうすると、本件J不動産については、不動産登記簿に所有者として登記されている原告甲ではなく、亡Bに帰属するというべき特段の事情があると認められ、亡Bを本件相続の開始時における所有者と認定すべきである。
 想う相続税理士
想う相続税理士
その趣旨や意味合いをきちんと理解する必要があります。