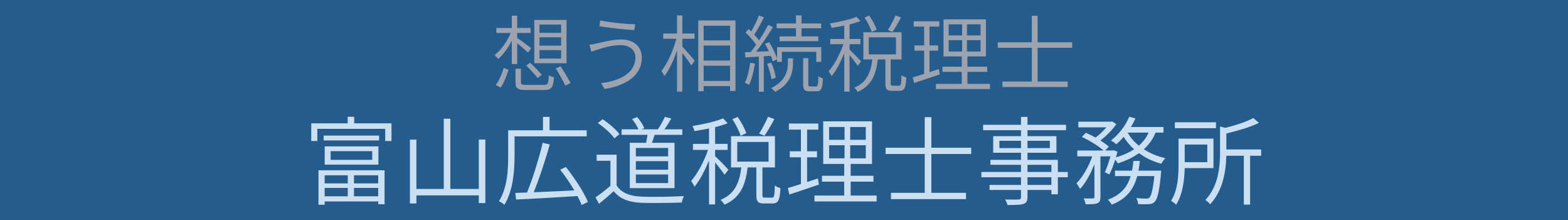相続税専門税理士の富山です。
今回は、保険料贈与プランの注意点について、お話します。
コンテンツ
相続対策・相続税対策としての保険料贈与プラン
「保険料贈与プラン」と呼ばれるモノがあります。
相続対策・相続税対策をする必要がある財産をお持ちの方が、その対策としてご自分で保険に入るのではなく、お子さんやお孫さん等に現金を贈与し、その贈与を受けたお子さんやお孫さん等が、その現金を保険料の支払いに充当し、保険に入る、というモノです。
うまく使えば大変効果的なのですが、1点注意すべき点があります。
それは、贈与を受けて保険に入った保険契約者(保険料負担者)が、相続後に保険契約をそのまま継続するのが困難になる場合がある、ということです。
ここでは、父Aさん・子Bさん・孫Cさんがいて、父Aさんの相続税対策として、保険料贈与プランを実行する場合について、見ていきます。
被保険者が贈与者なら保険契約が終了するので問題なし
子Bさんが父Aさんから現金の贈与を受け、被保険者を父Aさん・保険金受取人を子Bさんとする生命保険契約に加入したとします。
この場合、父Aさんが亡くなった時には、子Bさんに死亡保険金が支払われます。
子Bさんは、その死亡保険金について、一時所得として(自分の収入として)確定申告をする必要があります。
被保険者の死亡により、この生命保険契約は消滅します。
ですから、もう保険料を支払う必要はありません。
この場合には、特に問題がありません。
被保険者が受贈者なら保険契約が継続するので問題が発生する可能性あり
子Bさんが父Aさんから現金の贈与を受け、被保険者を子Bさん・保険金受取人を孫Cさんとする生命保険契約に加入したとします。
この場合、父Aさんが亡くなった時には、死亡保険金は支払われません。
父Aさんは被保険者ではないからです。
この生命保険契約のパターンは、子Bさんが自分にもしものことがあった時に、孫Cさんが困らないようにと願って入るモノです(もちろん、他の活用方法もあります)。
父Aさんが亡くなっても、子Bさんが亡くなっていないため、生命保険契約は継続します。
つまり、保険料の支払いも継続します。
子Bさんは、今までは父Aさんから保険料相当額の現金の贈与を受けていたため、保険料を支払うことができていましたが、父Aさんが亡くなった今後は、その贈与を受けることができません。
つまり、保険料の支払いが難しくなる可能性があるのです。
保険料の支払いが難しくなった場合の対応方法
このような場合、下記の対応を検討しましょう。
- 保険料の負担を軽くする(保険金額の減額等をする)
- 払済保険に変更する(保険契約は継続するが保険料の支払いを中止する)
- 保険契約を解約する(解約返戻金を受け取る)
対応方法と言っても、そのまま保険契約を継続して大きな保障を受けられることに比べると、デメリットが大きいかもしれません。
また、保険商品の種類によっては、そのダメージがかなり大きくなる場合もあります。
それだけではなく、保険商品の種類によっては、上記①②を選択することができない場合もあります。
このような状況を回避するためには、今後の保険料充当用の現金を相続で取得するなど、前もって資金繰り対策を検討しておきましょう。
できれば、上記①②③の対策をしない方がいいのです。
 想う相続税理士
想う相続税理士